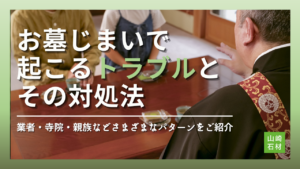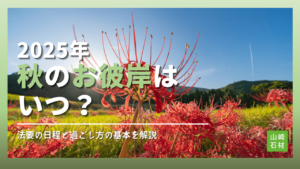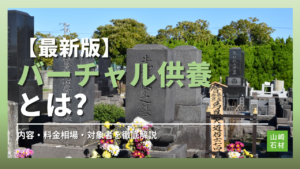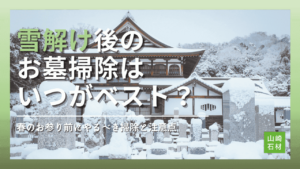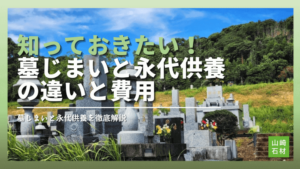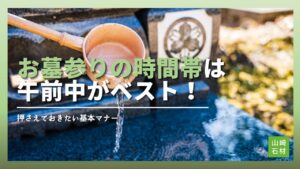女性
女性子どもがいないので、自分たち夫婦だけで入れるお墓を用意したい



将来、家族に迷惑をかけたくないけれど、どんな選び方をすればいいのかわからない
結論からお伝えすると、夫婦だけのお墓は法律上問題なく選ぶことができます。
今では樹木葬や永代供養墓、ネット墓などさまざまな選択肢があります。
なぜなら、少子化や家族のかたちが変わる中で、夫婦二人だけで完結できるお墓のニーズが年々高まっており、それに応える制度やサービスが全国で広がっているからです。
この記事では、夫婦墓の基本知識から費用の相場、種類ごとの違い、手続きの流れまで、後悔しない選び方をわかりやすく解説しています。
- 夫婦だけのお墓は法律上問題なく建てられる
- 夫婦墓の費用相場や種類ごとの特徴
- 後悔しない夫婦墓選びのポイント



この記事を読むことで、何を基準に選べばいいか、どんな準備が必要かがわかり、自分たちに合ったお墓を安心して選べるようになります。
ぜひ、今後の備えとして参考にしてみてください。
夫婦だけで入るお墓はできる?【結論可能です】


夫婦だけで入るお墓をつくることは可能です。
実際に、近年は夫婦二人だけのためのお墓を希望する方が増えており、各地の霊園や納骨堂でも対応できるプランが用意されています。
また、夫婦で生前に計画を立てておくことで、自分たちの希望を反映したお墓づくりができ、後のトラブルも避けやすくなるのも事実です。
たとえば「夫婦墓(ふうふぼ)」と呼ばれるお墓は、一緒に埋葬されることを前提としたつくりになっており、永代供養付きのものを選べば、管理の心配も少なくなります。
夫婦だけで入れるお墓のニーズは確実に増えてきており、希望に応じた形で準備することができます。
夫婦だけで眠りたいという価値観が増えている理由
大正大学 地域構想研究所の調査によると、少子化や家族構成の変化を背景に、夫婦や個人単位で供養・管理できる「継承者不要の墓」(合葬墓、納骨堂、樹木葬など)の需要が急増しています。
公営墓地では合葬墓が2004年から2024年までの20年で約4倍に増加、納骨堂も増設が進んでいます。
かつては親族みんなで同じお墓に入る「家墓」が一般的でしたが、今は家族の形や人との関わり方が多様になってきました。
たとえば、子どもがいない夫婦や再婚をした家庭では、親族とのつながりよりも、夫婦としての絆を大切にしたいと考えることが少なくありません。
また、親族との関係が薄い方や無理に人付き合いをしたくないという思いから、夫婦だけで完結するお墓を選ぶケースも見られます。
このような流れから、夫婦だけで入れる「夫婦墓」や「個人墓」など、継承者を前提としないお墓の人気が高まっています。
時代とともに、亡くなった後の在り方も、自分たちらしく選ぶ時代になっているのです。
子どもがいない夫婦に選ばれているお墓のタイプとは?


子どもがいない夫婦には、継承者がいなくても安心して利用できるお墓のタイプが選ばれています。
中でも多くの方に選ばれているのは、「永代供養」「樹木葬」「納骨堂」の3つです。
これらのタイプは、墓守りが必要ない点が大きな特徴です。
管理や供養は霊園や寺院が代行してくれるため、継承者がいなくても安心して利用できます。
永代供養
永代供養とは、遺族や継承者に代わって、霊園や寺院が長期間にわたり供養と管理を続けてくれる仕組みのことです。
お墓を継ぐ人がいなくても、安心して納骨できる方法として、近年とくに注目されています。
少子化や核家族化が進むなかで、「お墓を守る人がいない」「子どもに負担をかけたくない」という声が増えています。
永代供養を選べば、家族や親せきに世話を頼む必要がなく、自分たちの意思で供養の形を決めることができます。
費用もあらかじめ定額で支払うことが多く、後から維持費がかからない点も安心材料のひとつです。
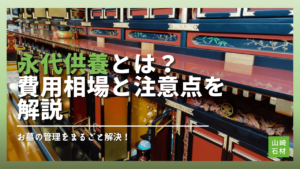
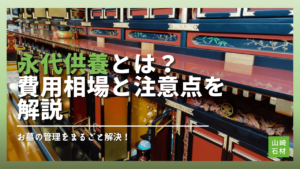
補足「永代管理」と「永代供養」の違い
「永代管理」と「永代供養」は言葉こそ似ていますが、その実態は異なります。
永代管理とは、将来お墓の継承者がいなくなった場合でも、管理者が責任を持って墓地の維持・管理を続ける制度です。草木の手入れや区画の保全など、物理的なお墓の存続を担保する点が特徴です。
また、「久遠」という制度は、いわゆる永代管理の仕組みであり、寺院や霊園によっては「管理費前払い制度」と呼ばれることもあります。
一方で、永代供養は管理だけでなく、定期的な供養(読経や法要など)を行う制度です。お坊さんが命日にお経を唱える、合同供養を行うなど、供養そのものが契約に含まれます。
樹木葬
樹木葬とは、墓石の代わりに木や草花を墓標として、自然の中に眠る埋葬方法です。
環境にやさしく、継承者がいなくても利用できることから、多くの人に選ばれるようになっています。
一般的なお墓と違い、樹木葬では墓石を使わず、一本のシンボルツリーや区画内の草木の近くに遺骨を埋葬します。
そのため、見た目が自然に溶け込み、静かで落ち着いた雰囲気の中で供養されたい方に向いています。
樹木葬についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。





樹木葬は自然に囲まれた環境にあることが多く、夏場には墓地にアブが飛び回ることがあります。
管理体制によっては、ある程度虫を軽減する対策を行っている場合もありますが、それでも完全に防ぐことは難しいのが実情です。
虫が苦手な方は、見学時に夏場の環境や管理状況を確認してから検討することをおすすめします。
納骨堂
納骨堂とは、屋内にある専用の建物に遺骨を安置する施設のことです。
天候や季節に左右されず、お参りしやすいことから、都市部を中心に利用が広がっています。
一般的な墓地と違い、納骨堂は建物の中にあり、エレベーターや空調が整った場所で落ち着いてお参りができます。
高齢の方でも移動が少なく、室内で快適に手を合わせられることが大きな特徴です。
納骨堂についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
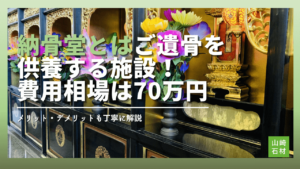
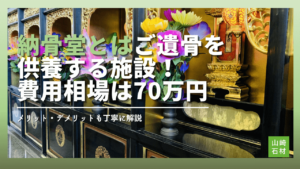
夫婦だけのお墓にかかる費用と相場感


夫婦だけのお墓にかかる費用と相場感について知っておきたいポイントは、大きく分けて以下の4つがあります。
- 一般的な夫婦墓の初期費用とその内訳
- 永代供養墓の場合
- 樹木葬の場合
- 期限付きのお墓の場合
これらを知らずにお墓を選んでしまうと、予想以上の出費が発生したり、将来的に管理面で後悔する可能性もあります。
お墓選びで失敗しないためにも、ぜひ参考にしてみてください。
一般的な夫婦墓の初期費用と内訳
一般的な夫婦墓の初期費用は、おおよそ100万円から200万円程度が目安とされています。
選ぶ墓地の場所や墓石の種類によって大きく差が出ますが、あらかじめ内訳を知っておくことで、無理のない計画が立てやすくなります。
夫婦墓の主な初期費用と内訳の目安については、下表をご覧ください。
| 項目 | 内容 | 相場の目安 |
|---|---|---|
| 永代使用料 | 墓地の区画を長期間使うための費用(※土地の購入ではない) | 約30万~100万円以上 |
| 墓石代 | 石の種類・デザイン・加工内容などによって異なる | 約50万円~ |
| 工事費 | 墓石の設置や基礎工事にかかる費用 | 約10万~30万円前後 |
| 管理費 | 墓地の維持・清掃などにかかる年単位の費用(初期一括払いのケースもあり) | 年間5千~1万円程度 |
| その他費用 | 名入れ・彫刻、納骨時の作業費など | 数万~10万円程度 |
夫婦墓を用意するにはいくつかの費用がかかりますが、内容をしっかり理解しておけば、後で困ることは少なくなります。
永代供養の場合
永代供養のお墓を夫婦で利用する場合、初期費用の相場はおおよそ50万円から150万円ほどが一般的です。
これは、継承者がいなくても供養や管理を施設側が長期間おこなってくれる点が大きな特徴です。
費用には、永代供養料のほか、納骨に必要な手数料や、夫婦二人分の埋葬スペースの確保費などが含まれます。
また、施設によっては位牌の設置や法要の手配が含まれることもあり、内容によって価格には差があるので確認しておきましょう。
合同供養は費用を抑えられ、個別に供養される形式を選ぶとやや高くなる傾向があります。
樹木葬の場合
夫婦で樹木葬を選ぶ場合の費用は、あわせて30万円から100万円程度が一般的な相場です。
自然の中で眠るという特徴があり、墓石を使わない分、費用をおさえやすい点が人気の理由です。
内訳としては、永代供養料のほか、埋葬スペースの使用料や、管理費などが含まれます。
墓標の代わりに植えられる木や花の種類、個別区画か合同区画かによっても金額は変わります。
また、夫婦で利用できるタイプの場合は、ひとつの区画に2名分の遺骨を納められる設計になっており、単身用に比べて広めのスペースが確保されています。
宗派を問わず利用できる施設が多く、生前に契約しておけば希望に沿った内容を選ぶことも可能です。
期限付きのお墓の場合
期限付きのお墓を夫婦で利用する場合、初期費用の相場は30万円から80万円ほどが目安です。
一定の期間だけ遺骨を安置し、その後は合葬墓などに移される仕組みで、費用をおさえたい方に選ばれています。
このタイプのお墓は、たとえば「33回忌まで」や「契約から50年間」など、あらかじめ期間が決められています。
期間が終わると、遺骨は共同の供養塔などに移され、引き続き永代供養が続けられるのが一般的です。
契約時にその後の対応も明記されているため、親族や関係者への負担が少ないことも安心材料といえるでしょう。
また、継承を前提としないため、子どもがいない夫婦や一代限りの供養を希望する方に適しています。
どちらかが先に亡くなったとき、夫婦墓はどう使う?


夫婦墓では、どちらかが先に亡くなった場合でも、もう一方が亡くなるまで遺骨を安置しながら待つことができます。
このような形式は「二人用」として設計されており、将来を見据えて準備されていることが特徴です。
どちらかが先に亡くなった場合の夫婦墓の一般的な流れは以下のとおりです。
- 先に亡くなった方の遺骨は、個別のスペースに安置される
- 残された配偶者が亡くなるまで、そのまま祀られる
- 二人揃った時点で、改めて一緒に供養される
- 合葬墓へ移すケースや、並んで個別に安置する方法もある
- 契約時に、供養の流れや対応方法について詳しい説明を受けられる
また、生前に希望を伝え合っておくことで、残された側も安心して供養を続けられるでしょう。
このように、夫婦墓はどちらかが先に亡くなっても、もう一方の存在を大切に考えながら使えるよう工夫されています。
家族墓から分けて夫婦だけの墓に移す方法と注意点


家族墓から分けて夫婦だけの墓に移す方法や注意点については、以下の2点を確認しておきましょう。
- 家族墓から夫婦墓に移すことは法律上可能なのか?
- 改葬に必要な手続きと流れ
順番に解説していきます。
家族墓から夫婦墓に移すことは法律上可能なのか?
家族墓に埋葬されている遺骨を、夫婦だけのお墓へ移すことは、法律上も可能です。
ただし、移動にはいくつかの手続きが必要となり、事前の確認と準備が欠かせません。
具体的には、「改葬(かいそう)」と呼ばれる手続きが必要で、これは埋葬されている遺骨を他の場所へ正式に移すことを意味します。
改葬手続きに必要な書類は、以下のとおりです。
| 改葬手続きに必要な書類 | 内容 |
|---|---|
| 埋葬証明書 | 現在遺骨がある墓地の管理者から発行してもらう |
| 受け入れ証明書 | 新しく遺骨を納める墓地や納骨堂から発行してもらう |
| 改葬許可申請書 | 市区町村役所に提出するための申請書(各自治体で様式が異なる) |
すべての書類がそろって許可が下りれば、正当な手続きとして移すことができます。
また、親族間の理解や承諾が必要になる場合もあるため、気持ちの面での調整も大切です。
宗教や地域によって考え方が異なることもあるので、事前に寺院や霊園の管理者へ相談すると安心できるでしょう。
改葬に必要な手続きと流れ
改葬を行うには、いくつかの書類と手続きが必要です。
正しく手続きをすれば、家族墓から夫婦墓へ遺骨を移すことは、法律上問題なく進めることができます。
| 書類名 | 提出先 | 内容の説明 |
|---|---|---|
| 埋葬証明書 | 現在の墓地管理者 | 遺骨が確かに埋葬されていることを証明する書類 |
| 受け入れ証明書 | 新しい墓地や納骨堂 | 移転先が遺骨を受け入れることを了承している証明書 |
| 書類名 | 提出先 | 内容の説明 |
|---|---|---|
| 改葬許可申請書 | 市区町村の役所 | 改葬を行うための申請書。上記2つの証明書と一緒に提出する必要あり |
書類がすべてそろい、内容に問題がなければ役所から「改葬許可証」が交付されます。
許可証を持って、遺骨を新しい墓地へ正式に移すことができます。
改葬は、法律に基づいた手続きであるため、事前に流れを理解しておけば安心です。
夫婦だけのお墓の後悔しない選び方4選


お墓選びで後悔しないためのポイントは以下のとおりです。
- 継承者がいなくても管理できるお墓を選ぶ
- 自分たちのライフスタイルに合った墓の種類を比較する
- 墓地の立地やアクセスを確認しておく
- 生前に夫婦でしっかり話し合っておく
事前にこれらの内容を理解しておけば、自分たちらしい納得のいくお墓を選ぶことができるようになります。
ひとつずつ見ていきましょう。
継承者がいなくても管理できるお墓を選ぶ
夫婦だけのお墓を選ぶときは、将来のことを考えて、継承者がいなくても管理してもらえるお墓を選ぶことが大切です。
一般的なお墓は、家族や親せきが代々守っていくことを前提に作られています。
しかし、継承者がいないと、将来的に無縁墓となり、撤去されたり、合同墓に移されたりする可能性があります。
そうならないように、最初から管理をすべて霊園や寺院に任せられる「永代供養墓」や「樹木葬」「納骨堂」などを検討すると安心です。
これらのお墓は、費用をあらかじめ支払っておくことで、供養や清掃などを長期間にわたって管理してもらえます。
自分たちのライフスタイルに合った墓の種類を比較する
自分たちのライフスタイルに合ったお墓の種類を比較して選びましょう。
立地や費用だけで決めるのではなく、供養の考え方や管理のしやすさなども含めて考える必要があります。
おすすめのお墓のタイプと特徴は以下のとおりです。
| 墓の種類 | 向いている方の特徴 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 樹木葬 | 自然の中で静かに眠りたい方 | 墓石を使わず、木や花を墓標にする。環境にやさしい。 |
| 納骨堂 | 天候に左右されず、快適にお参りしたい方 | 屋内施設で管理されており、バリアフリー対応も多い。 |
| 永代供養墓 | 子どもや親せきに負担をかけたくない方 | 管理や供養を霊園や寺院に任せられる。無縁墓にならない。 |
| ネット墓 | 遠方に住んでいて現地に行くのが難しい方 | インターネット上で供養ができ、費用も比較的安価。 |
ネット墓は、故人の情報をインターネット上に掲載し、オンラインでお参りできる仕組みです。
実際の墓地を必要としないため、費用を低く抑えられる点が魅力で、管理の心配もほとんどありません。
ネット墓について詳しく知りたい方は、こちらの記事をぜひご覧ください。
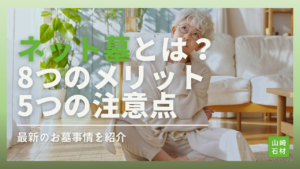
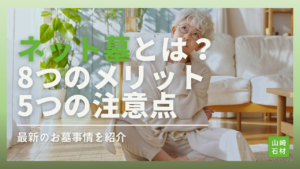



ネット墓と言えども、お骨は部地理的にどこかに埋葬する必要があるので、抑えておきましょう。
それぞれの特徴を知っておくことで、自分たちにとって無理のない形を選べるようになるでしょう。
墓地の立地や交通アクセスを確認しておく
墓地の立地や交通アクセスも事前に確認しておくことが大切です。
いくら理想的な供養の形であっても、場所が不便だと、お参りがしにくくなってしまいます。
とくに将来のことを考えると、高齢になっても無理なく通える場所かどうかが重要です。
駅からの距離や、駐車場の有無、坂道の多さ、バスの本数など、細かい点も見ておきましょう。
また、遠方に住む親せきが訪れやすいかどうかも、選ぶ際の大きな判断材料になります。
最近では、地図や口コミをもとに比較できるサイトも増えており、現地を見学する前に大まかな条件を確認することができます。
実際に足を運んでみて、雰囲気や周囲の環境を感じ取ることも後悔を防ぐポイントです。
生前に夫婦でしっかり話し合っておく
夫婦だけのお墓を選ぶなら、生前にしっかりと話し合っておくことが何よりも大切です。
どちらか一方だけで決めてしまうと、後になって「思っていた形と違った」と感じる可能性もあるため注意が必要です。
お墓の種類や場所、費用の負担方法、宗教的な考え方など、話し合うべきことは意外とたくさんあります。
たとえば、自然の中で眠りたいという思いや、子どもに負担をかけたくないという希望がある場合、それをお互いに共有しておくことで、納得のいく選択がしやすくなります。
また、早めに意思を確認しておくことで、万が一どちらかが先に亡くなっても、残された側が迷わず準備を進めることができます。
話し合いのタイミングは、元気なうちが理想です。
日常会話の中で少しずつ意見を出し合い、必要があれば家族や専門家にも相談するとよいでしょう。
まとめ


今回は、夫婦だけで入るお墓について、建てられるのかという疑問に対する答えから、手続きの流れ、費用の相場感、選び方のポイントまでを幅広く解説しました。
夫婦墓は法律上問題なく設けることができ、永代供養墓や樹木葬、納骨堂、ネット墓など、継承者がいなくても管理しやすい選択肢が増えています。
とくに、お墓選びを後悔しないためのポイントは以下のとおりです。
- 継承者がいなくても管理できるお墓を選ぶ
- 自分たちのライフスタイルに合った墓の種類を比較する
- 墓地の立地や交通アクセスを確認しておく
- 生前に夫婦でしっかり話し合っておく
本記事を参考に、自分たちの価値観やライフスタイルに合ったお墓の形を考えてみてください。