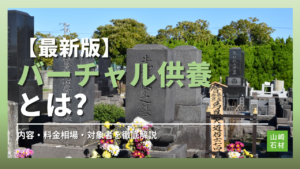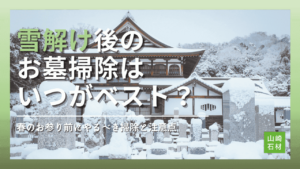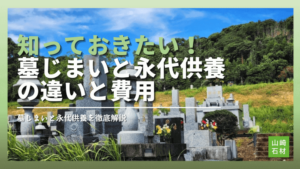女性
女性お墓参りには何を持っていけばいいの?



どうしても行けないときはどうすればいいの?
この時期は、このような悩みを感じる方が多くなります。
とくに初めてのお彼岸を迎える人にとっては、不安や疑問が多いのではないでしょうか。
この記事では、秋のお彼岸を心を込めて迎えるために知っておきたい基本情報とマナーを、わかりやすく解説します。
最後まで読むことで、お彼岸の準備に迷わず対応でき、安心してご先祖様をしのぶ時間を持てるようになります。
- 2025年秋のお彼岸の日程と意味
- お墓参りの基本マナーと準備
- 法要や供養の方法、行けない場合の対応



初めての方でも安心できるよう、わかりやすい言葉でご紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。
秋のお彼岸はいつからいつまで


秋のお彼岸は、9月の秋分の日を中心とした前後3日間の合計7日間を指します。
2025年の秋分の日は9月23日(火・祝)ですので、 2025年(令和7年)秋のお彼岸は9月20日(土)から9月26日(金)までの7日間です。
この期間は、太陽が真東から昇り真西に沈むことから、仏教ではあの世とこの世がもっとも通じやすい特別な時期と考えられています。
秋のお彼岸は、決まった日付ではなく毎年異なります。
秋分の日が正式に発表された後に日程を確認し、予定を立てておくと安心です。
お彼岸の中日と前後の意味の違い
お彼岸の中日と前後の意味の違い【早見表】
| 日程 | 名称 | 意味・役割 |
|---|---|---|
| 前半3日間 | 精進努力の期間 | 自分の心を整える期間(反省・内省) |
| 中日(秋分の日) | 感謝の日 | 昼と夜の長さが等しい特別な日。中道を象徴し、ご先祖様への感謝を伝える日 |
| 後半3日間 | 実践の期間 | 整えた心を行動に移す期間 |
お彼岸の中日とは、「秋分の日」のことをいいます。
中日は、昼と夜の長さがほぼ同じになる特別な日で、仏教では「中道(ちゅうどう)」を象徴する大切な日とされています。
中日はご先祖様への感謝を伝える日であり、仏壇やお墓に手を合わせるのにもっともふさわしいとされます。
一方で、前後の3日間にはそれぞれ意味があり、前半の3日間は「自分の心を整える期間」、後半の3日間は「その心を行動で示す期間」とされています。
たとえば、前半には日頃の反省や思いやりの気持ちを育て、後半には掃除やお墓参りなどを通してそれを実践するという具合です。
つまり、中日は感謝を伝える日、前後は心を整え実践する日ということです。
お彼岸にお墓参りへ行く時間帯はいつ?
お彼岸のお墓参りは、午前中から日中の明るい時間帯に行くのが一般的です。
とくに午前10時から午後3時ごろまでが、マナーとしても安全面でもおすすめの時間帯とされています。
これは、仏事や法事は日が昇っている間に行うのが基本とされているためです。
また、明るいうちであれば足元も見やすく、掃除やお供えなどの作業もしやすいため、ご高齢の方や小さなお子様がいる場合にも安心です。
夕方や夜のお墓参りは、地域によっては縁起が良くないとされることもあり、避ける人が多い傾向にあります。
どうしても都合がつかない場合を除き、日中のうちに手を合わせ、ご先祖様に感謝の気持ちを届けるのがよいでしょう。
お墓参りに行く時間帯については、以下の記事でも詳しく解説しています。
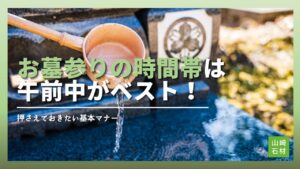
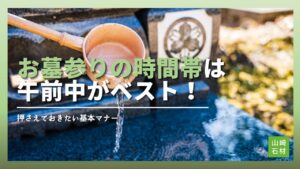
なぜ、お彼岸のお墓参りが必要なのか?


お彼岸にお墓参りをするのは、ご先祖様に感謝の気持ちを伝えるためです。
私たちが今ここに生きているのは、過去の命の積み重ねがあるからこそ。
その「つながり」を実感し、大切にするための行いが、お彼岸のお墓参りなのです。
お彼岸は、春分・秋分の日を中日とした七日間で、昼と夜の長さがほぼ同じになる特別な時期です。
仏教では、この世(此岸)とあの世(彼岸)がもっとも近づくとされ、心を整え、ご先祖様との距離を感じやすい期間だと考えられています。
この時期にお墓を訪れ、手を合わせることで、感謝の気持ちや家族の絆をあらためて見つめ直すことができます。
忙しい日々の中で忘れがちな心の余裕や、命のありがたみを感じる貴重な時間でもあります。
お墓参りに持っていくべきもの
お墓参りの際に何を持っていけばよいのか迷う方に向けて、必要な持ち物を大きく分けて5つご紹介します。
- お供え用の生花
- 線香、ろうそく、マッチやライター
- お供え物
- 掃除道具
- 宗教用品
準備が不十分だと、現地で困ってしまったり、礼を欠く形になってしまうこともありえます。
ひとつずつ見ていきましょう。
お供え用の生花
お墓参りの際には、故人をしのぶ気持ちを込めて生花を供えることが大切です。
選ぶ花は、色合いが落ち着いており、香りが強すぎず長持ちするものが望まれます。
一般的には、菊、カーネーション、リンドウなどがよく使われます。
季節感を大切にするなら、秋にはリンドウやススキなどもよいでしょう。
一方で、バラのようにトゲのある花や、香りが強すぎる花は避けるのがマナーです。
花は一対(二束)で持参し、花筒の水を交換してから丁寧に供えます。
線香、ろうそく、マッチやライター
お墓参りに欠かせないのが、線香とろうそく、そして火をつけるための道具です。
線香には、心を清める意味があり、香りが辺りに広がることで場を整えるといわれています。
ろうそくは線香に火を移す役割を持ち、供養の場を明るく照らす象徴でもあります。
マッチやライターも忘れずに持参し、着火しやすい風よけ付きのライターを使うと便利です。
また、火の取り扱いには十分注意し、風が強い日はとくに安全に配慮しましょう。
お供え物
お彼岸のお墓参りでは、故人の好物や季節の果物などを供えることで、感謝や思い出を表現します。
ただし、選び方や供え方にはいくつかの注意点があります。
果物では、りんご、みかん、ぶどうなど、香りが強すぎず常温でも傷みにくいものがよいでしょう。
お菓子であれば、包装されたまま供えることで清潔に保つことが可能です。
また、肉や魚、アルコールなど、宗派やお寺の方針によっては避けるべきものもあるため、事前に確認すると安心できます。
なお、供えた後は持ち帰るのが基本です。カラスや虫による被害を防ぐ意味でも、供えたまま帰らないようにしましょう。
掃除道具
お墓の掃除道具として持って行くものには、雑巾、スポンジ、バケツ、ほうき、ちり取り、ゴミ袋などが挙げられます。
墓石の表面はやさしく水拭きし、コケや汚れはスポンジで落としましょう。
草取り用の手袋や軍手もあると便利です。
掃除の後は、水を入れ替え、花筒や線香立ても清潔に整えましょう。
きちんと掃除を行うことで、お墓が清らかに保たれ、気持ちも自然と落ち着いてきます。
宗教用品
お墓参りの際に用意しておきたい宗教用品には、数珠、経本、お布施などがあります。
これらは宗派や家庭の習慣によって異なるため、必要なものを確認しておくと安心です。
数珠は手を合わせるときに使うもので、祈りを形にする道具です。
お経を唱える際には経本があるとより丁寧な供養になります。
また、法要や僧侶の読経がある場合には、お布施も必要です。
お布施は白封筒またはのし袋に包み、表書きを「御布施」「御供」などと記し、心を込めて渡しましょう。
お彼岸での服装のマナー5選


お彼岸にふさわしい服装のポイントは、大きく分けて以下の5つです。
- 紺、グレーなどの落ち着いた色の服を選ぶ
- ロゴや柄物は避け、無地やシンプルなデザインを選ぶ
- 肌の露出は控えめにする
- 靴は歩きやすく、土を汚さないものを選ぶ
- 子どもにも落ち着いた色と動きやすい服を着せる
場にそぐわない服装で参列すると、ご先祖様や周囲の方への配慮に欠ける印象を与えてしまうかもしれません。
ここからは、場の雰囲気を大切にしながら、季節や動きやすさにも配慮した服装の選び方をご紹介していきます。
紺、グレーなどの落ち着いた色の服を選ぶ
お彼岸のお墓参りでは、紺やグレーなどの落ち着いた色合いの服装がふさわしいとされています。
派手な色は避け、控えめで清潔感のある色を選ぶことが礼儀にあたります。
黒ほど堅苦しくなく、しかし目立ちすぎない紺、グレー、ベージュなどの色味は、年齢や性別を問わず着こなしやすく、場の雰囲気にもなじみます。
とくに秋のお彼岸では、季節感を意識しながら、落ち着いたトーンの羽織や上着を選ぶと安心です。
カジュアルな服であっても色味が整っていれば、きちんとした印象を与えることができます。
ロゴや柄物は避け、無地やシンプルなデザインを選ぶ
お墓参りの服装では、できる限り無地やシンプルなデザインのものを選ぶのが基本です。
目立つロゴや柄物は、供養の場にふさわしくないとされるため注意が必要です。
たとえば、大きな英字やキャラクターが入ったTシャツ、カラフルなプリント柄のシャツなどは、場所によってはマナー違反と受け取られることもあります。
特別な服を用意しなくても、普段着の中からシンプルなものを選べば問題ありません。
肌の露出は控えめにする
お彼岸のお墓参りでは、肌の露出をできるだけ控えることがマナーです。
露出の多い服装は、供養の場にそぐわないとされ、場の雰囲気を乱す原因にもなります。
ノースリーブや短いスカート、深く開いた襟元などの服は避け、肩や脚がしっかり隠れる服装を選びましょう。
暑い時期であっても、羽織ものや長袖のシャツを重ねるなど工夫することが大切です。
また、下着の透けが目立つ薄手の服にも注意が必要です。
靴は歩きやすく、土を汚さないものを選ぶ
お墓参りの際は、歩きやすくて墓地の環境に配慮した靴を選びましょう。
サンダルや高いヒール靴は避け、安定感のある靴が望まれます。
多くの墓地は土や石が多く、足場が平らでないこともあります。
そのため、ヒールのある靴や白い靴は汚れやすく、転倒の危険もあるため不向きです。
スニーカーやローヒールの靴であれば動きやすく、掃除や供物の準備もしやすくなります。
靴を脱ぐ場面がない場合でも、足元が整っていると全体の印象もよくなります。
子どもにも落ち着いた色と動きやすい服を着せる
子どもを連れてお墓参りをする場合も、落ち着いた色合いと動きやすい服装を意識することが大切です。
大人と同じく、礼儀を意識した装いが望まれます。
たとえば、黒、紺、グレーなどのTシャツやシャツ、膝丈のズボンやスカートなどは見た目も落ち着いており動きやすさも備えています。
キャラクターの入った服や蛍光色などの派手なデザインは避けたほうが無難です。
お彼岸の法要はどこで行う?


お彼岸の法要は、主に菩提寺(先祖代々のお墓があるお寺)で行われるのが一般的です。
この時期には、多くの寺院で「彼岸会(ひがんえ)」と呼ばれる合同法要が行われ、家族や親族が集まり、ご先祖様に感謝の気持ちを伝えます。
法要は本堂や法要堂で執り行われることが多く、僧侶の読経にあわせて焼香を行います。
また、希望すれば個別に法要をお願いすることも可能です。
この場合は、日時の相談や会場の確認が必要になります。
自宅やお墓の前で行う出張法要を選ぶ方もおり、高齢者や遠方の家族がいる場合に選ばれることがあります。
お寺での法要は、宗派ごとの作法に沿って進められるため、事前に準備や服装について確認しておくと安心です。
| 法要の場所 | 特徴・内容 | 選ばれる理由 |
|---|---|---|
| 菩提寺(本堂・法要堂) | 一般的な法要の場。僧侶の読経と焼香を行う | 先祖代々の墓があるお寺で、形式に沿った供養ができる |
| 合同法要(彼岸会) | 複数の家族が一緒に参加。お寺が日時を設定して開催 | 日程が決まっており、準備が比較的楽。費用も抑えやすい |
| 個別法要 | 希望日時・内容をお寺と調整して執り行う | 個別に丁寧な供養を行いたい家庭向け |
| 出張法要(自宅・墓前) | 僧侶が自宅や墓地に訪問し、読経を行う | 高齢者や遠方の家族が参加しやすい。柔軟な対応が可能 |
お彼岸の法要の申込み方法
お彼岸の法要を希望する場合は、早めにお寺へ連絡して予約を取ることが大切です。
彼岸の時期は希望が集中しやすいため、余裕を持って申し込むことで、希望する日時に法要を行いやすくなります。
まずは、菩提寺や希望する寺院へ電話または直接訪問します。その際、「秋のお彼岸に法要をお願いしたいのですが」と伝えましょう。
次に、以下の項目について具体的に相談します。
- 法要の種類(合同法要か個別法要か)
- 希望する日時や時間帯
- 参加する家族の人数
- 法要を行う場所(本堂・自宅・墓前など)
申し込みの際に、以下の点も一緒に確認しておくと安心です。
- お布施の目安(相場や包み方など)
- 持参すべきもの(数珠・供物・線香など)
- 服装や集合時間の注意点
お寺によっては、申込用紙の提出やインターネットでの受付を行っている場合もあります。指定された方法に沿って正式に申し込みましょう。
申し込み内容をもとに、当日の持ち物や服装を準備し、時間に余裕を持って参列できるようにしておきます
気になる点があれば、事前に再度確認しておくと安心です。
申し込み後は、案内された内容に沿って準備を進め、当日は時間に余裕を持って訪れるとよいでしょう。
不明な点は早めに問い合わせることで、当日の不安やトラブルを防ぐことができます。
秋のお彼岸にお寺に持参するお布施の相場


秋のお彼岸で法要をお願いする際は、感謝の気持ちとしてお布施をお寺にお渡しします。
金額に明確な決まりはありませんが、法要の形式によって相場の目安があります。
お彼岸のお布施の相場は以下のとおりです。
| 法要の形式 | お布施の相場 | 備考 |
|---|---|---|
| 合同法要(彼岸会) | 3,000円〜10,000円 | 他の家族と合同で行う読経。比較的負担が軽い。 |
| 個別法要(本堂など) | 10,000円〜30,000円 | 一家族のみで行う読経。丁寧な供養を希望する方向け。 |
| 出張法要(自宅・墓前) | 10,000円〜30,000円程度 + 交通費5,000円前後 | 僧侶が訪問。移動にかかる実費も別途必要な場合あり。 |
ただし、地域の習慣やお寺の方針によって金額は異なるため、申し込み時に直接確認するのが安心です。
秋のお彼岸に関するよくある質問


秋のお彼岸について多くの方が疑問に思いやすい内容についてご紹介します。
安心してお彼岸の行事にのぞむために、ひとつずつ確認していきましょう。
お彼岸にお墓参りできないときはどうする?
どうしてもお彼岸にお墓参りへ行けない場合でも、気持ちを込めた供養は十分に可能です。
お墓に足を運べなくても、ご先祖様を思う心を行動で示す方法はいくつもあります。
たとえば、自宅で仏壇にお線香や花を供え、静かに手を合わせることも立派な供養です。
仏壇がない家庭であっても、写真や遺影の前で感謝の気持ちを伝えるだけでも意味があります。
また、菩提寺に連絡を入れて、代理供養や塔婆供養をお願いする方法もあります。
遠方に住んでいる方や体調の都合で行けない方でも、お寺を通じて供養の意志を届けることができます。
最近では、お布施や供物を郵送で受け付けている寺院も増えており、忙しい方にとって重宝されています。



どうしても行けないときは、ネット墓という方法もあります。
スマートフォンやパソコンからオンラインで手を合わせられるサービスで、遠方の方や忙しい方にも利用されています。
ネット墓についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
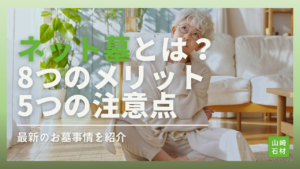
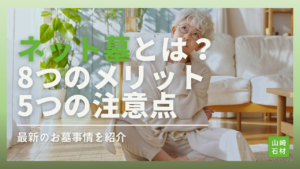
小さい子供を連れてお墓参りに行っても大丈夫?
小さな子供を連れてお墓参りに行くことは、まったく問題ありません。
むしろ、命のつながりを学び、ご先祖様への感謝を伝える良い機会になります。
仏教では、子供が手を合わせる姿は尊く、歓迎される行動とされています。
とはいえ、静かな場所であるため、事前に「ここは大切な場所だから静かにしようね」と伝えておくと安心です。
走り回ったり、大声を出したりしないように、簡単に説明するだけでも子供の行動は落ち着きます。
また、帽子・水筒・タオルなどを準備し、熱中症や虫さされの対策も忘れないようにしましょう。
まとめ
今回は、秋のお彼岸について、その日程から法要の申し込み手順、持参物、マナーまで解説しました。
お彼岸とは、ご先祖様に感謝の気持ちを伝える仏教行事であり、秋分の日を中日とした7日間がその期間とされます。
2025年の秋分の日は9月23日(月・祝)であるため、秋のお彼岸は9月20日から9月26日までとなります。
法要は主に菩提寺で行われ、合同法要や個別法要、出張法要などの形式があり、準備や申し込みには事前の確認が欠かせません。
また、服装や持ち物のマナー、どうしてもお墓参りに行けない場合の供養方法についても触れ、誰でも安心してお彼岸を迎えられるようにまとめました。
この記事を通して、秋のお彼岸を心を込めて迎えるための基本を理解し、ご先祖様とのつながりを大切にする時間にしていただければ幸いです。