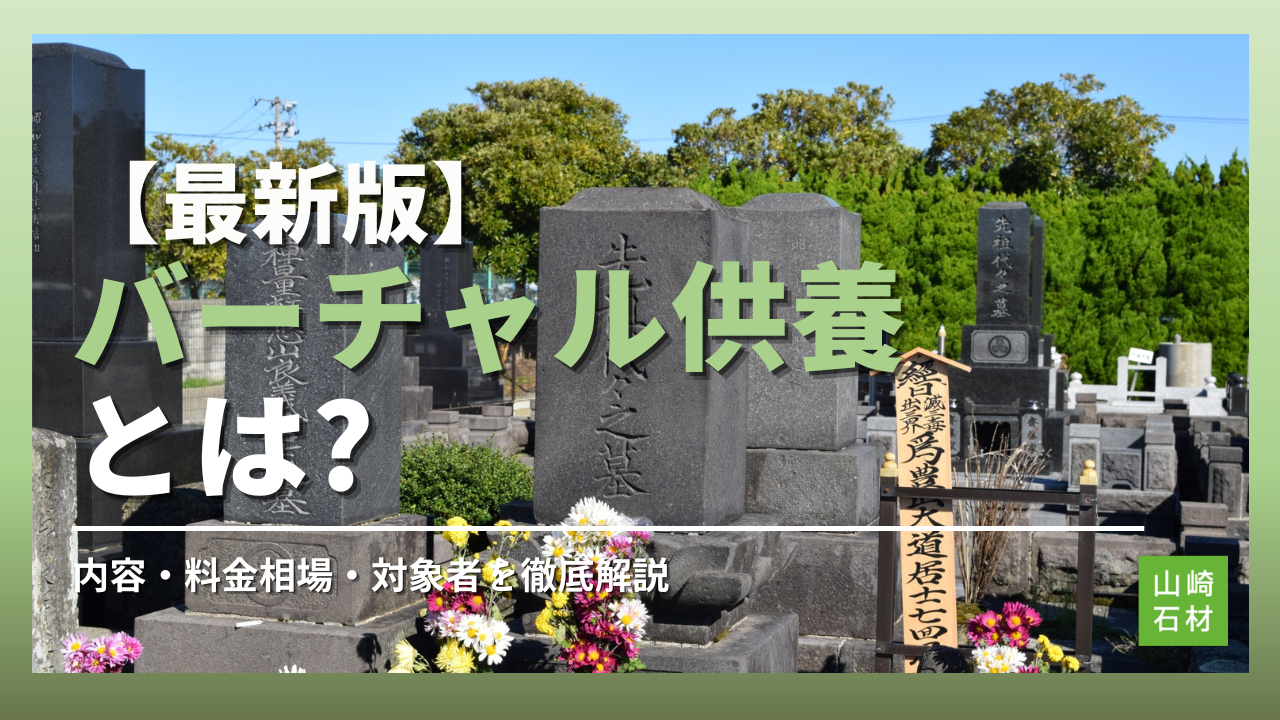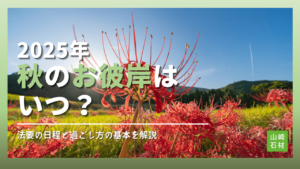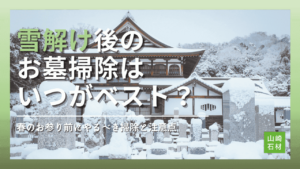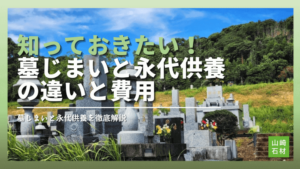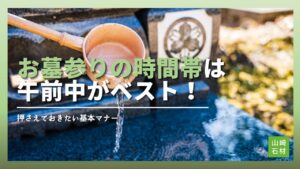女性
女性お墓参りに行きたいけれど、実家が遠い。



体調の理由で外出できない…。
結論からお伝えすると、バーチャル供養は場所や時間にとらわれずに故人を偲べる、新しい供養の方法です。
和尚による読経をオンラインで受けられたり、メッセージや写真を投稿して家族と共有できるため、現代の暮らしに合った形で心を込めた祈りを続けられます。
なぜなら、核家族化や高齢化でお墓参りが難しい人が増え、供養のあり方にも変化が求められるようになったからです。
伝統を大切にしながらも、無理なく実践できる手段としてバーチャル供養が広がっています。
この記事では、バーチャル供養の具体的な内容、料金相場、リアル供養との違い、どんな人に向いているか、さらにお参り代行との関係についても分かりやすく解説します。



最後まで読むことで、自分や家族に合った供養の形が見つかり、安心して選べるようになりますよ。
バーチャル供養とは


バーチャル供養とは、インターネットを通じて行う新しい形の供養方法を指します。
自宅にいながら和尚による読経を依頼できたり、オンライン上で故人へのメッセージや写真を投稿できる点が特徴です。
遠方や海外に住んでいる人でも気持ちを届けられるため、時間や場所にとらわれずに供養の機会を持つことができます。
リアル供養との違い
バーチャル供養とリアル供養の大きな違いは、行う場所と方法にあります。
リアル供養は実際にお墓や寺院に足を運び、和尚の読経や焼香を通じて故人を偲ぶ伝統的な形です。
一方でバーチャル供養は、インターネットを利用し、画面越しに祈りを届ける方法で、物理的な移動を必要としません。
近年は高齢や遠方といった事情から、直接現地に行くことが難しい方も増えています。
バーチャル供養はそうした状況に応じ、和尚の読経をオンラインで依頼できたり、家族が同じ場に集まらなくても、同じ時間に祈りを共有できる仕組みを持っています。
つまりリアル供養は「場に集うこと」で心をつなげるのに対し、バーチャル供養は「時間を合わせること」で絆を確かめられる方法といえるでしょう。
どちらも故人を大切に思う気持ちは変わらず、その形が異なるだけで目的は共通しています。
バーチャル供養の具体的な内容


バーチャル供養でできることは、大きく分けて4つあります。
- 故人へのメッセージや写真を投稿して供養できる
- 家族・親族で供養の場を共有できる
- 命日やお盆などに自動で供養が実施される
- バーチャル供養の料金相場
それぞれの特徴について順番に解説していきます。
和尚による読経やお経をオンラインで実施できる
バーチャル供養では、和尚による読経やお経をオンラインで依頼できます。
現地に足を運ばなくても、パソコンやスマートフォンを通じて、僧侶の声に耳を傾けながら祈ることが可能です。
従来はお寺や墓前に集まる必要がありましたが、遠方に住んでいたり、高齢や体調の理由で移動が難しい方には大きな負担となっていました。
オンライン供養であれば、画面を通じて同じ時間にお経を聴けるため、心を落ち着けて供養を行うことができます。
また、法要の日程に合わせて予約をすれば、自宅に居ながらも伝統的な儀式に参加できるのも利点です。
つまり、和尚の読経をオンラインで受けられる仕組みは、環境や距離に左右されずに供養を続けられる新しい形といえるでしょう。
故人へのメッセージや写真を投稿して供養できる
バーチャル供養では、故人への想いをメッセージや写真として投稿し、オンライン上に残すことが可能です。
紙のお手紙や実際のお供えとは異なり、言葉や画像をデジタルの形で共有できる点に特徴があります。
家族や友人は、供養専用のページにアクセスして思い出を投稿することができ、遠く離れていても互いの気持ちを確かめ合えます。
文章だけでなく写真を添えることで、その人の姿や思い出の場面が鮮明に伝わり、より深い供養の場となります。
時間を選ばず投稿できるため、心に浮かんだ瞬間に気持ちを届けられる点も魅力です。
このように、メッセージや写真の投稿は、個人の祈りを形にしながら、家族全体で思いを共有できる方法といえるでしょう。



山崎石材では、この仕組みを「雲のものがたり」というサービスでご提供しております。
雲のものがたりの公式サイトはこちら
家族・親族で供養の場を共有できる
バーチャル供養では、離れて暮らす家族や親族が同じ場を共有できます。
オンライン上に設けられた供養のページに集まることで、時間や場所をそろえることが難しい場合でも、一緒に故人を偲ぶことが可能です。
これまでの供養は、親族が集まるための移動や日程調整が欠かせませんでした。
しかし現代は、海外勤務や地方での生活など、全員が同じ場所に集まるのが難しい状況も少なくありません。
オンラインの供養であれば、各自が自宅や職場から参加でき、同じ画面を通して祈りを捧げることができます。
その様子が記録として残る場合もあり、後から確認できるのも安心です。
命日やお盆などに自動で供養が実施される
バーチャル供養の特徴のひとつに、命日やお盆などの大切な日に合わせて、自動で供養を行える仕組みもあります。
事前に日付を登録しておくと、その日に合わせてお経や祈りが実施されるため、忘れることなく供養を続けられます。
従来は命日やお盆を意識して予定を調整する必要があり、忙しい現代人には負担となる場合もありました。
自動で供養が行われることで、離れて暮らしていても安心して気持ちを託せるほか、家族全員が同じタイミングで祈るきっかけになります。
また、通知機能が備わっているサービスでは、供養の開始を知らせてくれるため、参加しやすい点も魅力です。
バーチャル供養の料金相場


バーチャル供養の料金は、サービス内容や依頼する方法によって幅があります。
一般的には一回あたり数千円から一万円前後が中心で、読経や法要を依頼する場合はやや高めに設定されることが多いです。
年間契約型のプランを設けている事業者もあり、その場合は数万円程度になる例も見られます。
費用に差があるのは、和尚の読経が含まれるか、メッセージや写真投稿のみで行うかといった提供内容の違いによるものです。
また、命日やお盆に自動で供養を行う仕組みを備えているサービスでは、定期的な運営管理費が加わるため料金が上がる傾向にあります。
一方で、簡単なオンライン供養や追悼ページの利用のみであれば、低価格で利用できるケースもあります。
バーチャル供養に向いている人の特徴4選


バーチャル供養に向いている人の特徴は、大きく分けて以下の4つです。
- 実家が遠方でお墓参りに行けない人
- 海外に住んでいて日本での供養が難しい人
- お墓じまいや永代供養を検討している人
- 高齢や身体的な理由で外出が難しい人
それぞれの特徴について、見ていきましょう。
実家が遠方でお墓参りに行けない人
実家から離れて暮らしている人にとって、定期的にお墓参りをするのは容易ではありません。
現実問題として、交通費や移動時間の負担が大きく、忙しい生活の中では思うように供養の時間を確保できないことも多いです。
バーチャル供養であれば、自宅に居ながら僧侶の読経を依頼したり、オンライン上に設けられた場で故人を偲ぶことが可能です。
インターネットを通して手を合わせることで、距離に左右されずに気持ちを届けられる仕組みが整っています。
また、家族や親族と同じページを共有できるため、離れていても同じ思いを持って祈ることができます。
海外に住んでいて日本での供養が難しい人
海外で生活している人にとって、日本にあるお墓を訪れることは簡単ではありません。
場合によっては、長期休暇や高額な渡航費が必要になり、命日やお盆に合わせて帰国するのはほとんど不可能な場合もあります。
しかし、バーチャル供養を利用すれば、現地からでもオンラインで供養に参加でき、日本にいる家族と気持ちを分かち合えます。
とくに和尚による読経をライブ配信で聴けるサービスでは、海外に居ながらも本格的な供養を体験することができます。
さらに時差に合わせて供養の時間を調整できる仕組みがあるため、生活環境に合った形で利用できるのもメリットです。
お墓じまいや永代供養を検討している人
近年は少子化や核家族化の影響で、お墓を維持するのが難しくなり「お墓じまい」や「永代供養」を考える家庭が増えています。
墓石の撤去や管理費の負担は大きく、子や孫に重荷を残したくないと考える人も少なくありません。
そのような場面で、バーチャル供養は新しい選択肢となります。
オンライン上に故人を偲ぶ場を設けることで、物理的なお墓がなくても祈りの場所を守ることができます。
さらに永代供養とあわせて利用すれば、伝統的な儀式の安心感と、デジタルならではの継続性を両立できます。
永代供養についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。


高齢や身体的な理由で外出が難しい人
高齢や体調の問題で外出が難しい方にとって、お墓参りは大きな負担になりがちです。
階段や坂道が多い墓地まで出向くのは危険を伴い、付き添いが必要になる場合もあります。
仮にバーチャル供養を利用すれば、自宅から安全に参加できるため、身体に無理をかけずに祈りを続けられます。
画面越しに和尚の読経を聴いたり、家族と同じページで故人を偲んだりすることで、孤独を感じずに供養を行えるのも利点です。
また、日常生活の中で供養の習慣を取り入れやすく、気持ちの区切りをつけやすい点も大きな特徴です。
補足|お参り代行という選択肢もある


バーチャル供養に抵抗があるが、実際にお参りに行くのも難しいと思う方には「お参り代行」という選択肢もあります。
ここからは、お参り代行の特徴について説明していきます。
お参り代行とは現地に足を運べない人のための代行サービス
お参り代行とは、利用者の代わりに現地のお墓へ出向き、清掃やお花の交換、焼香などを行うサービスのことです。
仕事や体調の都合でお墓参りができない人に代わり、専門スタッフが丁寧に供養を行い、その様子を写真や報告書で伝えてくれます。
近年は遠方に暮らす家族が増え、命日やお盆に合わせてお墓を訪れるのが難しい状況が多くなりました。
そのため、現地に行けなくても供養の気持ちを届けられる手段として注目されています。
また、依頼者は報告を通じてお墓の状態を確認できるため、安心して任せられるのも大きなメリットです。
バーチャル供養と組み合わせることもできる
お参り代行は、バーチャル供養と組み合わせて利用することも可能です。
現地ではスタッフが清掃や焼香を行い、オンライン上では家族や親族が祈りを合わせるという具合です。
バーチャル供養だけでは「実際のお墓に手を合わせられない」という不安を感じる人もいます。
しかし、お参り代行を組み合わせることで、実際の現場での供養とデジタル上での祈りを同時に実現できます。
さらに、記録として残される写真や動画を共有すれば、離れた家族もお墓の様子を知ることができ、安心感が高まるでしょう。
まとめ
今回は、バーチャル供養の基本的な内容や料金相場、利用に向いている人について解説しました。
バーチャル供養は、僧侶による読経をオンラインで受けられたり、メッセージや写真を投稿して家族と共有できるなど、場所や時間にとらわれずに故人を偲べる新しい供養の方法です。
料金の目安は、一回あたり数千円から一万円前後が多く、年間契約型のサービスでは数万円になる場合もあります。サービス内容によって費用が異なるため、事前に確認することが大切です。
とくに、バーチャル供養に向いている人は以下のとおりです。
- 実家が遠くてお墓参りができない人
- 海外に住んでいる人
- お墓じまいや永代供養を検討している人
- 高齢や身体的な理由で外出が難しい人
従来の供養に比べ、柔軟に取り入れやすい点が大きな特徴ですが、サービスによって方法やサポート内容に差があるため、自分や家族の状況に合ったものを選ぶことが重要です。
まずは複数のサービスを比較し、安心して供養を続けられる仕組みを検討してみてください。
山崎石材工業では、無料にてお墓のことをご相談いただけます。もし、遠方でお墓参りに行くことができない方はお気軽にご相談ください。